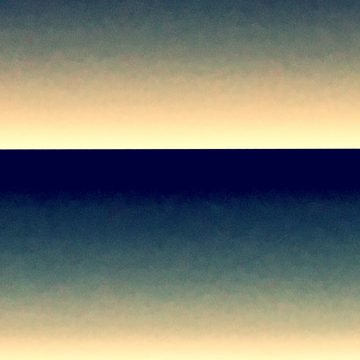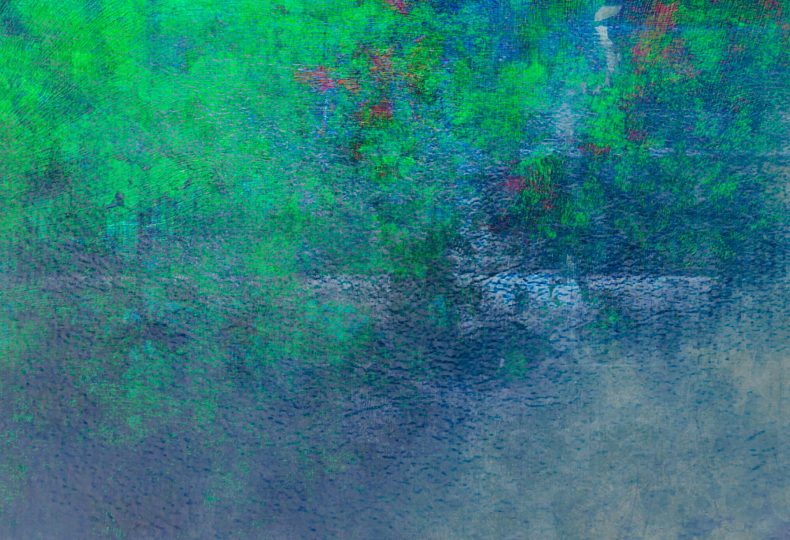
今からできるビジネス倫理学(実践編)
前編(理論編)では、ビジネスに倫理が必要な時代だからこそ、そうした倫理が独りよがりにならず、権威を振りかざすことのないよう、学問としてビジネス倫理学を行なう意義があることを強調した。
もちろん、学問の知見は、ビジネスの実践に還元すべきだろう。経営学でも、ビジネススクールで学ぶ分析フレームワーク(マイケル・ポーターのファイブ・フォース分析や、ジェイ・バーニーのVRIO分析など)は、経営学の知見をビジネスパーソン向けのメソッドとして作り直したものである。
そこで、ビジネス倫理学を通して得た知見を、ビジネスパーソン向けのメソッドとして作り直してみたい。以下では、そんなビジネス倫理学のメソッドを三つ紹介する。
1.ソクラテス・メソッド:アマチュアとして思考する
企業からの依頼を受けて、ビジネス倫理学について講演させてもらうことがある。しかし、まだ30代の私が、会場にいる50代、60代に向けて、倫理について壇上から講釈を垂れても、説得力はない。むしろ、企業人としての倫理を語る資格をもつのは、私でなく会場にいるプロの方々である。では、アマチュアの私に何ができるのか。
「自分の良心に反した仕事をしたことはありますか」。「直近の会議で一番偉そうにしていたのは誰ですか」。私は、会場にいる人々に向けて倫理について語ってもらおう、とマイクを差し出すようにしてきた。新入社員も役員も関係なく聞いて回り、組織のなかで個人の良心が果たす役割や、会議における権力関係について、会場の人々と考えていく。企業人でないアマチュアである私だからこそできることだ、と思っている。

このやり方には、「ソクラテス・メソッド」という名前が付いている。古代ギリシアの哲学者ソクラテスは、自分が何も知らない「アマチュア」であることに自覚的であった。だからこそ、その道のプロに聞いて回り、彼ら・彼女らが当然視した倫理観でさえ疑い、思いもしない次元から思考することができた。
ビジネスパーソンは、ビジネスのプロであり、特定の倫理観をもっている。それは仕事をしていくうえで、なくてはならないものだろう。しかし、それゆえに当然視しがちになってしまう部分があるはずだ。前編(理論編)では、顧客を最優先すべきだ、という倫理に切り込んだ。当たり前とみなされていることにも疑問をもつアマチュアとしての思考は、こうした倫理観に変革をもたらすだろう。
ソクラテス・メソッドをビジネスにどう活用するか。私の提案は、哲学者を会社に呼んでみる、というものである。哲学者は、たんなるアマチュアでなく、「プロのアマチュア」だからである。既に、グーグル社やアップル社では、哲学者をフルタイムで雇っている。グーグル社の社内哲学者(インハウス・フィロソファー)だったデイモン・ホロヴィッツは、「カントの義務論に従うべきか。ミルの帰結主義に従うべきか」と問いかけて、携帯電話のデータをどう取り扱うべきか業界内で倫理が定まっていないことを指摘する。哲学者の問いかけは、思いもよらない発見につながるだろう。
2.CSRメソッド:当たり前にやっていることを「倫理的」だとアピールする
私が担当する大学のゼミでは、富士ゼロックスが主幹となって、大学と企業を結びつけ、地域人材を育成する「志プロジェクト」に参加している。学生たちは、地元企業へ訪問し、社長や従業員へのインタビューや工場見学を行い、彼ら・彼女ら目線での会社案内を作成する(【2018年度】杉本俊介ゼミ「志プロジェクト」成果報告会)。

2019年から、このプロジェクトをさらに発展させて、CSR(企業の社会的責任)パンフレットを作成しようと考えている。CSRは、今でもビジネス倫理学の重要なテーマであり、学生たちが授業で学んでいるものだからだ。しかし、これまでCSR活動に取り組んだことがない企業にとって、どのような活動がCSRに該当するのか判断するのも難しい。
私は、当たり前にやっていることを「CSR」と呼んでみたらどうか、と提案している。もちろん、どんな事業でもそう呼べるわけではない。ISO(国際標準化機構)は、組織の社会的責任に関するガイドラインを出している。また、グローバル・レポーティング・イニシアチブ(GRI)は、サステナビリティ報告書の規準を発表している。さいたま市でも、CSRチェックリストを作成している。何がCSRと呼べるかを考える際、これらの規準を参考にすればよいだろう。
当たり前にやっていることをアピールする。このメソッド(「CSRメソッド」と呼ぶことにする)を、倫理一般に拡張し、当たり前にやっていることを「倫理的」と呼んでアピールしてみたらどうか。何が倫理的と呼べるかについて、まずは私たちの良心が規準になるだろう(次いで、前編(理論編)で紹介した、功利主義などを参考にしてみるとよいだろう)。
たしかに、倫理をアピールすることは非常に照れくさいし、周囲の鼻につく。私たちは当たり前にやっていることを、たとえそれが立派な行ないだとしても、「立派だ」と自慢したりしない。本当に倫理的な人間は、自分のことを「倫理的」だとは認識しないし、そう言わないのである。倫理学では、これを「無知の徳」と呼び、倫理的な人間の特徴の一つに数えたりする。
しかし、企業は、法人とは言うものの、人間ではない。企業は、倫理的な人間の特徴に従う必要はないのだ。当たり前に倫理的なことをしていれば、それを「倫理的」だとアピールし、宣伝してみるべきだ。
3.アレント・メソッド:労働と仕事(台所とタイプライター)を区別する
哲学カフェというものがある。街中のカフェなどで、飲み物を片手に一般参加者同士で特定のテーマについて話し合うイベントである。パリのカフェで生まれ、その後世界中に広がっている。
私も、働く意味について話し合う哲学カフェを開いたことがある。しかし、働くことへの理解が参加者によって違い、話が噛み合わないこともあった。その反省から、働くとはそもそも何か、を自分なりに整理してみた。
参考にしたのは、20世紀の哲学者ハンナ・アレントの1958年の著作『人間の条件』(ちくま学芸文庫、1994年)である。アレントは、この本の中で、労動と仕事を敢えて区別する(アレントはまた、これらを活動(アクション)と区別するが、今回は触れない)。アレントによれば、労働(レイバー)とは、日々の生活の糧を得ることである。他方で、仕事(ワーク)とは、物を作り出すこと(ものづくり)である。
アレントは次のように説明する。労働によって、日々の生活の糧が生産され消費される。たとえば、台所でオムレツを料理するのが、労働である。それは、私たちの口に入り、血となり肉となる。つまり、生命の循環に組み込まれる。
それに対して、仕事は、生命の循環を超えた人工的な物の世界を作り出す。自分の仕事の成果を後世まで残したい人もいるだろう。成果を残し築き上げる世界は、生命を超えて永続するからだ。たとえば、タイプライターで記事を書くのが、仕事である。(台所とタイプライターの対比は、アレント自身による(前掲書、訳者解説))。
アレントのように労働と仕事を区別することを、「アレント・メソッド」と呼びたい。もちろん、この区別は一般的でない。アレントも、過去の人間の営みを豊かに記述するための区別であることを強調する。それでも、この区別を現代ビジネスに対する発見術(ヒューリスティックス)とすることで見えてくるものがある。それは、ものづくりの本質である。
アレントによれば、労働にとって重要なのは、消費である。労働とは、生み出した途端に消費されるほかない仕方で生産する、生命循環の一部だからである。それに対して、仕事にとって重要なのは、使用である。仕事とは、使用し続けるのに耐えられる物を作り出すことだからである。
ところが、現代において、仕事は労働化されてしまっている。実際、日々の生活の糧を得るために、ものづくりをする人も多い。それが悪いわけではない。だが、仕事が労働化されることで、その成果がただ消費されるだけのものに変わってしまう。仕事が労働化されるこの時代だからこそ、仕事を労働から切り離すアレント・メソッドが有効になる。
たとえば、街中至るところで、買ったばかりのビニール傘が置き去りにされている。携帯電話は、新機種が出るたびに、新しいものに買い替えられる。売れ筋の本は、一読されるやいなや古本屋で安売りされる。アレントに言わせれば、ビニール傘や携帯電話の生産、売れる本の執筆は、もはや、ものづくりではない。それは、生産され消費されるための労働であり、生命の循環を超え出ることがないからだ。これは、使い捨ては悪い、という環境やマナーの問題ではないことに注意したい。耐久性をもつ物の世界を作り続けていくか、という人間の働き方の問題なのである。
アレント・メソッドを使って、自身のものづくりを振り返ってほしい。生み出した途端に消費されるほかない仕方で、生産していないだろうか。アレントの言い方では、それは労働であっても仕事ではない。本来のものづくりは、世界を作り出すことだからである。